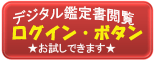← 前のページへ / 次のページへ →
7 晩年を迎えて
①妻と息子の死
60年という長期にわたってわが国を支配してきた江戸幕府が瓦解して、明治新政府が発足した。時に1868年(明治元)、杏雨59歳のことだった。
その翌年、活気づいてきた世の中とは逆に、杏雨にまたも不幸が襲う。
一番上の長男で、父と同じ咸宜園に学んでその秀才ぶりを発揮し、その後医師として将来を嘱望されていた玄斎(幼名:慶蔵)が33歳という若さで他界してしまったのだ。さらには息子の後を追うように、それから一ケ月後、最愛の妻まで逝ってしまったのだ。
②聴秋庵を建てる
杏雨は、若い頃は京阪などへの旅を重ねたが、32歳からは大分県外へは一歩も出ていない。多くの画人が中央を目指す中で、杏雨はそれとは逆の方向をたどった。交友を深めながら近隣の自然に親しみ、腰を落ち着けて、淡々とまさに自娯のために絵を描き続けてきた。そんな欲の無い杏雨が何よりも欲しかったのが自分の庵(別荘)であった。なにしろ画名が高まってからの杏雨邸には来客が多く、手狭であり、ゆっくりくつろげるゆとりが無かった。
杏雨は、62歳のとき大野氏より後妻を娶った。そして1872(明治5)年、悲しみから立ち直った杏雨は、戸次の中津留に「聴秋庵」という別荘を新築した。
③万国博覧会に出品
聴秋庵を新築した明治5年、杏雨の絵がオーストリアのウィーンで開催された世界万国博覧会の絵画部門の日本代表で出品されるという栄誉に輝いた。このときの出品作品は「耶馬渓青緑山水図」であったが、ウィーンの人たちは杏雨の絵の精巧さに驚いたという。
幕末の動乱によって、画法を大きく変えざるを得なかった杏雨であったが、その中にあって、杏雨はかつての綿密な画法による秀作を描くことがあった。あの激しい急変する時代の中でも、それに抗して自分を見失わないで努力したことが万国博覧会出品という輝かしい結果として表れたのかも知れない。
④殺到する絵の注文
杏雨の画名が高まるにつれて、絵の注文が殺到するようになった。そのために65歳頃から極端に多作になっている。依頼されて断りきれず、このころは一日に数点を描き上げることも珍しくなかったという。これは、この頃南画が全国的に大流行となったことに起因しているのであろう。
⑤杏雨の門人たち
杏雨の名声が高まるにつれて、杏雨に教えを請う人が多くなり、門人の数も増えていった。直接、間接に杏雨から影響を受けた画人は30数名に上ったという。また、直接学んだ画人は17名だった。
⑥最晩年の杏雨
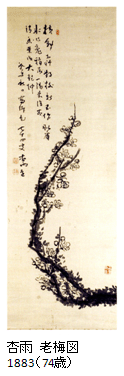 杏雨の淡々とした生き方は老年を迎えてもほとんど変わらなかった。山や川に出かけ、春になると梅や桜を愛で、友人や門人と庵で酒を酌み交わしながら歓談するのが何よりの楽しみであった。若い頃から健脚だった杏雨だが、69歳で判田の孤塚岳に登ったのを最後に山歩きを止めている。
杏雨の淡々とした生き方は老年を迎えてもほとんど変わらなかった。山や川に出かけ、春になると梅や桜を愛で、友人や門人と庵で酒を酌み交わしながら歓談するのが何よりの楽しみであった。若い頃から健脚だった杏雨だが、69歳で判田の孤塚岳に登ったのを最後に山歩きを止めている。
1879年(明治12)、70歳になってから、杏雨は病に臥すことが多くなった。それでも南画への情熱は失せず、もともと目をよく患っていた杏雨だったが、ついに70歳の冬、右目を失明してしまう。それでも、ひっきりなしに依頼される絵を次々と描き上げていった。しかし、その後めっきり体力が衰え、1884年(明治17)6月9日、杏雨は75歳の生涯を静かに閉じた。
杏雨没後、南画の全国的流行にかげりが見え始め、次第に衰退期へと移っていく。実質的には、明治20年(1887)、東京美術学校の創立の時に、フェロノサ、岡倉天心らの意向による西欧化の流れに圧しつぶされた。絵画に文学(賛詩)を取り込むような手法は西欧にはなく邪道であると南画科が排除された。
⑦杏雨に学ぶ
 杏雨の生涯をたどってみると、その生きざまに共感することが多い。確かに杏雨は富豪の家に生まれ、経済的には何不自由ない身ではあった。周りには父や兄をはじめ多くの文化人に囲まれ、絵を描くとう行為が自然に出来る環境でもあった。しかし、こういう環境の下に育てば誰もが優れた画人になれるというものではない。むしろそういう好環境に恵まれると、それに甘んじてぬくぬくと人生を送りがちだ。しかし、杏雨は違っていた。常に一所に安住して満足するということが無かった。肉親の死などの悲しみを乗り越え、恩師竹田の教えどおり、基本を忠実に、自己の画風の確立のために絶え間ない努力と工夫を重ね、創造への挑戦欲を持ち続けた。そして竹田のまねで終わることなく、わが国の南画史上に燦然と輝く、卓越した色彩センスに支えられた杏雨独自の画法をうち立てた。この一事だけでも杏雨を評価できる。
杏雨の生涯をたどってみると、その生きざまに共感することが多い。確かに杏雨は富豪の家に生まれ、経済的には何不自由ない身ではあった。周りには父や兄をはじめ多くの文化人に囲まれ、絵を描くとう行為が自然に出来る環境でもあった。しかし、こういう環境の下に育てば誰もが優れた画人になれるというものではない。むしろそういう好環境に恵まれると、それに甘んじてぬくぬくと人生を送りがちだ。しかし、杏雨は違っていた。常に一所に安住して満足するということが無かった。肉親の死などの悲しみを乗り越え、恩師竹田の教えどおり、基本を忠実に、自己の画風の確立のために絶え間ない努力と工夫を重ね、創造への挑戦欲を持ち続けた。そして竹田のまねで終わることなく、わが国の南画史上に燦然と輝く、卓越した色彩センスに支えられた杏雨独自の画法をうち立てた。この一事だけでも杏雨を評価できる。
杏雨はまた、人と酒と自然を愛し、こだわりのない、欲の無い生き方をした。杏雨は権力とか、地位とか、自分の名声のために画を描き学問をするということからは縁遠い生き方をした。若き日に、京阪の地で頼山陽とか浦上春琴などの超一流の文人から画を認められながら、中央での華々しさを求めるのではなく、活躍の舞台はほとんど県内で、それも戸次の近隣が主体であった。その中で杏雨は、多くの友人や知人と交友を深め、自然と共に生きた。近隣の山々に登り、野を歩き、梅や桜を愛で、大野川で舟遊びし、氏神に詣で、地道に自娯のために絵を描き続けた。名利を求めることなく、まさに淡々と、悠々とした生き方であった。
このページのトップへ戻る
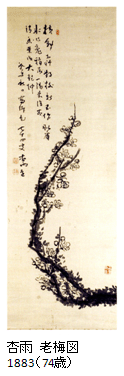 杏雨の淡々とした生き方は老年を迎えてもほとんど変わらなかった。山や川に出かけ、春になると梅や桜を愛で、友人や門人と庵で酒を酌み交わしながら歓談するのが何よりの楽しみであった。若い頃から健脚だった杏雨だが、69歳で判田の孤塚岳に登ったのを最後に山歩きを止めている。
杏雨の淡々とした生き方は老年を迎えてもほとんど変わらなかった。山や川に出かけ、春になると梅や桜を愛で、友人や門人と庵で酒を酌み交わしながら歓談するのが何よりの楽しみであった。若い頃から健脚だった杏雨だが、69歳で判田の孤塚岳に登ったのを最後に山歩きを止めている。 杏雨の生涯をたどってみると、その生きざまに共感することが多い。確かに杏雨は富豪の家に生まれ、経済的には何不自由ない身ではあった。周りには父や兄をはじめ多くの文化人に囲まれ、絵を描くとう行為が自然に出来る環境でもあった。しかし、こういう環境の下に育てば誰もが優れた画人になれるというものではない。むしろそういう好環境に恵まれると、それに甘んじてぬくぬくと人生を送りがちだ。しかし、杏雨は違っていた。常に一所に安住して満足するということが無かった。肉親の死などの悲しみを乗り越え、恩師竹田の教えどおり、基本を忠実に、自己の画風の確立のために絶え間ない努力と工夫を重ね、創造への挑戦欲を持ち続けた。そして竹田のまねで終わることなく、わが国の南画史上に燦然と輝く、卓越した色彩センスに支えられた杏雨独自の画法をうち立てた。この一事だけでも杏雨を評価できる。
杏雨の生涯をたどってみると、その生きざまに共感することが多い。確かに杏雨は富豪の家に生まれ、経済的には何不自由ない身ではあった。周りには父や兄をはじめ多くの文化人に囲まれ、絵を描くとう行為が自然に出来る環境でもあった。しかし、こういう環境の下に育てば誰もが優れた画人になれるというものではない。むしろそういう好環境に恵まれると、それに甘んじてぬくぬくと人生を送りがちだ。しかし、杏雨は違っていた。常に一所に安住して満足するということが無かった。肉親の死などの悲しみを乗り越え、恩師竹田の教えどおり、基本を忠実に、自己の画風の確立のために絶え間ない努力と工夫を重ね、創造への挑戦欲を持ち続けた。そして竹田のまねで終わることなく、わが国の南画史上に燦然と輝く、卓越した色彩センスに支えられた杏雨独自の画法をうち立てた。この一事だけでも杏雨を評価できる。